記事内に商品プロモーションを含む場合があります

退職は人生の転機ですが、手続きは思いのほか複雑で、多くの人が不安を感じています。退職手続きを誤ると、後々のトラブルにつながる可能性があるため、正しい知識を持つことが重要です。この記事では、退職手続きの流れや必要な書類、退職後の各種手続きなどをまとめました。
記事を読めば、退職手続きの流れを把握し、スムーズに手続きを進められます。正しい知識を身に付けて退職手続きに臨み、不安なく次のステップへ踏み出しましょう。
退職手続きの流れ

退職手続きの主な流れは、以下のとおりです。
- 退職の意思表示
- 退職願・退職届の提出
- 業務の引き継ぎと調整
- 取引先への挨拶
- 退職当日の対応
退職の意思表示
退職の意思表示は、退職手続きの重要なステップです。まずは上司や人事部門に退職の意向を口頭で伝えましょう。退職理由を簡潔に説明し、退職希望日を明確に伝えることが大切です。会社の規定や慣例に従い、適切なタイミングで伝えてください。退職の意思を伝える際は、以下を意識するとスムーズになります。
- 感謝の気持ち
- 引き継ぎ・残務処理
- 退職願・退職届
- 退職スケジュール
ポイントを押さえると、円滑な退職手続きが可能です。丁寧かつ誠実な対応を心がけると、良好な関係を保ちながら退職プロセスを進められます。
» 退職を伝えるタイミングは?よくあるトラブルと対策について解説
退職願・退職届の提出
退職願や退職届の提出は、退職手続きの中で重要なステップです。会社に対して正式に退職の意思を伝える書類になるため、適切に作成し提出する必要があります。氏名や所属部署、退職予定日や退職理由を記載しましょう。提出時期は、通常は退職予定日の1〜2か月前が目安です。
ただし、具体的な期限は会社の就業規則によって異なるため、あらかじめ確認しておきましょう。提出方法も会社の規定に従う必要があります。提出後は、受理を確認するために署名をもらいましょう。署名のコピーを保管しておくと安心できます。退職願と退職届には違いがあります。
退職願は退職の希望を、退職届は退職が決定したことを伝えるものなので、会社の方針に合わせて適切な書類を選びましょう。
» 介護職の主な退職理由と円満に伝えるポイントを解説
業務の引き継ぎと調整

業務の引き継ぎと調整は、退職を円滑に進めるうえで重要です。現在の業務内容や進行中のプロジェクトの状況を整理しましょう。引き継ぐべき内容が明確になります。引き継ぎ先の担当者を決定し、引き継ぎ資料を作成してください。引き継ぎ資料の一例は以下のとおりです。
- 業務マニュアル
- 手順書
- 重要な情報やノウハウ
引き継ぎ期間のスケジュールを設定したうえで、計画的に進めましょう。未完了の業務については、対応方針を決定してください。関係部署や取引先への連絡と調整も忘れずに行いましょう。引き継ぎ状況の進捗確認と報告を定期的に行い、スムーズな引き継ぎを心がけてください。
データや資料の整理と引き渡し、アカウントやパスワードの変更・引き継ぎも重要です。適切な手順で引き継ぎを行うと、スムーズに完了できます。
取引先への挨拶
取引先への挨拶は、退職する際に欠かせない重要なステップです。適切な挨拶をすると、信頼関係を損なわず、スムーズに引き継げます。取引先への挨拶の方法には、直接訪問と挨拶状の送付の2種類があります。直接訪問する場合は、退職日の1~2週間前が適切なタイミングです。
挨拶状を送る場合も、同じ時期に届くよう準備しましょう。挨拶の際に伝えるべき内容は以下のとおりです。
- 退職の報告
- 感謝の気持ち
- 後任者の紹介
- 引継ぎの説明
取引先への挨拶の範囲や方法は、上司や人事部門と相談して決めましょう。取引先への丁寧な挨拶は、会社との良好な関係を維持するためには欠かせません。
退職当日の対応

退職当日は、最後の出勤日として多くの手続きや挨拶が控えています。スムーズに退職を完了するためには、計画的な行動が重要です。具体的な流れは以下のとおりです。
- 出勤
- 挨拶
- 業務引き継ぎ確認
- デスク整理
- 会社支給品返却
- 書類確認・提出
- 社員証返却
- 挨拶回り
- 送別会参加
- 最終退社
手順どおりに進めると、退職日を円滑に過ごせます。業務の引き継ぎ確認や書類の提出は重要なので、漏れがないか注意しましょう。
退職手続きで会社に提出・返却するもの
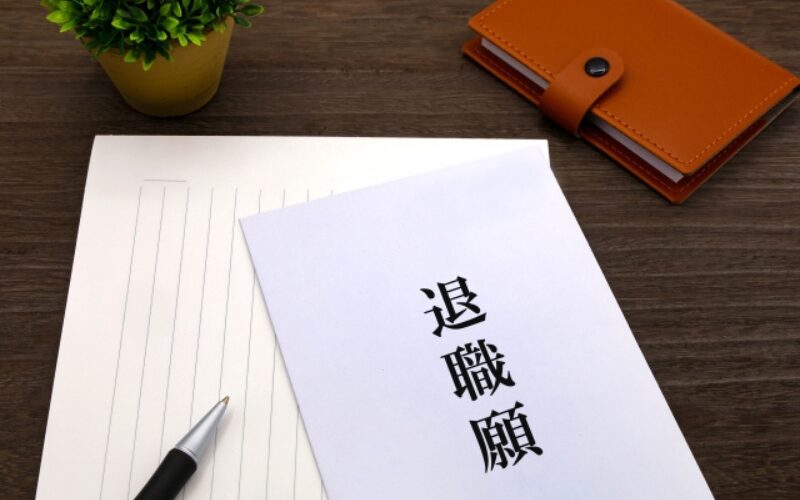
退職手続きを円滑に進めるには、会社に提出・返却するものを事前に準備することが大切です。退職時に会社に提出・返却するものを以下にまとめました。
- 退職願・退職届
- 健康保険証
- 会社から支給された物品・資料
退職願・退職届
退職願・退職届は、会社に対して正式に退職の意思を伝える重要な文書です。一般的には、退職を希望する日の1〜2か月前に提出します。基本的な記載事項は以下のとおりです。
- 宛先
- 日付
- 氏名
- 退職理由
- 退職希望日
退職理由は詳しく書く必要はなく、簡単な記載で問題ありません。作成方法は会社の方針に従いましょう。複数部数用意し、控えを保管しておきましょう。提出先は直属の上司か人事部門です。退職願・退職届を提出すると、正式に退職の意思を会社に伝えられます。
健康保険証

健康保険証は、退職時に会社へ返却する必要があるものです。返却する際は、健康保険の資格喪失日(通常は退職日の翌日)を確認しましょう。返却前にコピーを取り、家族の分も含めて全ての保険証の返却を忘れないでください。健康保険証を紛失した場合は、会社に相談しましょう。
再発行や始末書の提出が必要になる場合があります。返却を忘れると、後日請求される可能性があるため、注意が必要です。返却時には、会社から健康保険資格喪失証明書を受け取りましょう。任意継続被保険者制度を利用する場合など、詳しくは会社の担当者に確認してください。
健康保険証を返却した後は、国民健康保険や新しい職場の健康保険に加入する必要があります。退職後は、健康保険の切り替えを忘れずに行いましょう。
会社から支給された物品・資料
会社から支給された物品や資料は、退職時に必ず返却しましょう。具体的には、以下の物品や資料を返却する必要があります。
- 社員証やIDカード
- パソコンやタブレット
- 携帯電話やスマートフォン
- オフィス用品
- ユニフォームや制服
- 名刺
- 会社のマニュアルや機密文書
セキュリティカードや鍵、業務用ソフトウェアのライセンスや法人カードなども忘れずに返却しましょう。返却漏れがないよう、入社時に支給されたものや業務で使用していたもののリストアップがおすすめです。不明な点がある場合は、人事部門や上司に確認しましょう。
退職手続きで会社から受け取るもの
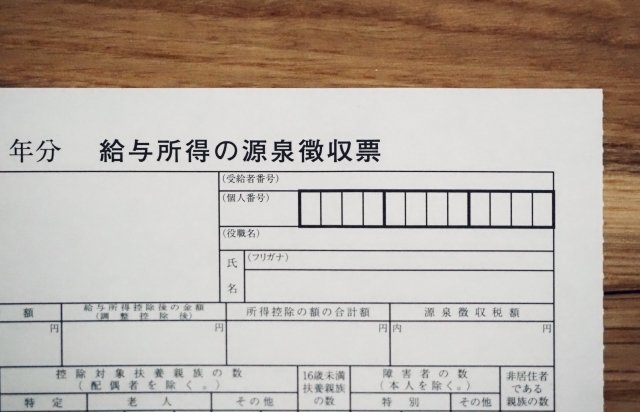
退職時に会社から受け取る書類や物品を以下にまとめました。
- 離職票
- 源泉徴収票
- 雇用保険被保険者証
- 年金手帳
離職票
離職票は、雇用保険の受給資格を証明する公的書類です。会社を退職した後、失業給付を受けるために必要です。離職票には、離職理由や勤務期間、賃金などの情報が記載されています。退職後、会社から受け取る重要書類の一つです。離職票には離職票-1と離職票-2の2種類があります。
原則として、離職票は退職してから2週間ほどで手元に届きます。紛失した場合でも再発行ができます。離職票を受け取ったら、大切に保管しておきましょう。失業給付の申請時に必要となるため、なくさないように注意してください。
源泉徴収票
源泉徴収票は、会社から発行される重要な税務書類です。前年の給与所得と源泉徴収税額が記載されており、確定申告や年末調整の際に必要になります。通常、源泉徴収票は退職時または翌年1月末までに発行されます。原本は1部のみ発行されるため、大切に保管してください。
紛失した場合には再発行はできますが、手続きに時間がかかる場合があります。源泉徴収票の主な用途は以下のとおりです。
- 転職先への提出
- 確定申告の証明書類
- 収入・納税額の確認
氏名や住所、給与金額や源泉徴収税額は注意深くチェックしましょう。退職金がある場合は、別途「退職所得の源泉徴収票」も発行されます。源泉徴収票を紛失してしまった場合は、速やかに会社に連絡し、再発行を依頼してください。税務関連の手続きに必要な重要書類なので、適切に管理しましょう。
雇用保険被保険者証
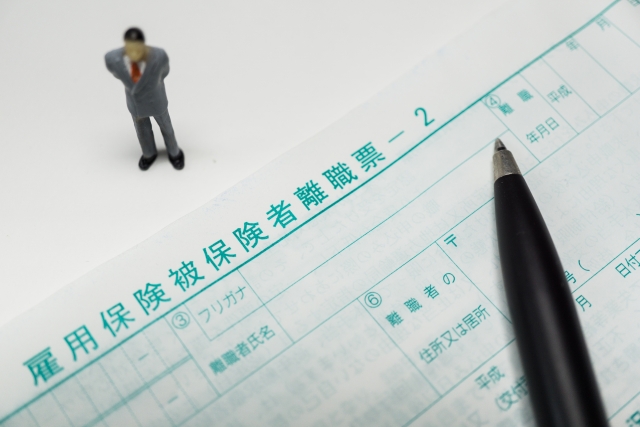
雇用保険被保険者証は、雇用保険に加入していたことを証明する大切な書類です。退職時に会社から渡されます。雇用保険被保険者証には、以下の情報が記載されています。
- 氏名
- 生年月日
- 被保険者番号
- 雇用保険の加入期間
- 資格取得年月日
雇用保険被保険者証は、次の就職先で必要になります。失業給付を受ける際にも必要になるので、大切に保管しましょう。退職後すぐに就職しない場合も保管が必要です。紛失してしまってもハローワークで再発行できます。
年金手帳
年金手帳は、年金加入期間を証明する重要な書類です。年金手帳には基礎年金番号が記載されており、原則として1人1冊発行されます。年金手帳は次の就職先に提出し、国民年金の手続きや年金相談、請求時に利用する書類です。
退職手続き後の流れ
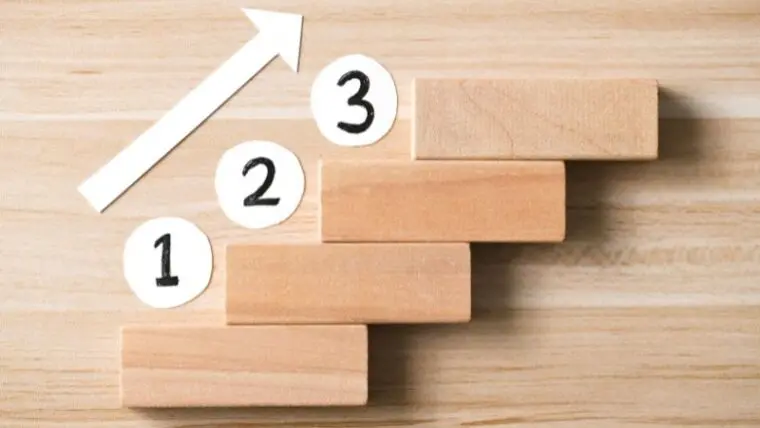
退職手続き後の流れを以下にまとめました。
- 健康保険の切り替え
- 国民年金への加入手続き
- 雇用保険(失業保険)の申請
- 住民税と所得税の手続き
健康保険の切り替え
健康保険の切り替えは、退職後に行う必要がある重要な手続きです。健康保険の切り替え先は、以下のとおりです。
- 国民健康保険
- 新しい職場の健康保険
- 扶養家族としての加入
- 任意継続被保険者制度
切り替えの際は、手続きの期限や必要書類を確認しましょう。新しい保険証を取得したら、旧保険証は返却する必要があります。高額療養費制度の継続利用や特定健康診査の受診権利についても確認しておきましょう。傷病手当金や出産手当金を受給中の場合は、継続して受給できるかも確認が必要です。
国民年金への加入手続き
国民年金への加入手続きは、退職後の重要な手続きの一つです。手続きは年金事務所または市区町村の国民年金窓口で行います。退職日の翌日から14日以内に手続きをする必要があります。本人確認書類と年金手帳、または基礎年金番号通知書を持参しましょう。具体的な手続きの流れは以下のとおりです。
- 国民年金加入申込書の記入
- 保険料の納付方法の選択
- 保険料免除や猶予制度の申請
保険料の納付方法は口座振替やクレジットカード、納付書から選択できます。マイナンバーカードがある場合は、オンラインで手続きできます。配偶者の扶養に入る場合は、第3号被保険者の手続きが必要になるため注意しましょう。国民年金への加入は将来の生活を支えるため、退職後は忘れずに手続きを行いましょう。
雇用保険(失業保険)の申請

雇用保険(失業保険)の申請は、退職後の生活を支える重要な手続きです。申請の流れを知っておくと、スムーズに手続きを進められます。ハローワークで雇用保険受給資格者証の交付を受けましょう。離職票や雇用保険被保険者証、身分証明書を持参し、求職申込書を記入します。
記入後は受給資格の確認と失業認定日の指定を受けてください。申請後は、7日間の待機期間を経て失業給付の支給が始まります。失業認定日にはハローワークへと来所し、失業の認定を受けてください。受給期間は原則1年間ですが、求職活動を継続し、定期的に失業認定を受ける必要があります。
再就職した場合は速やかにハローワークに報告してください。不明点があれば、ハローワークの窓口で相談しましょう。
住民税と所得税の手続き
住民税と所得税の手続きは、退職後の重要な手続きの一つです。住民税は市区町村から納付書を受け取るため、納付先や期限を確認してください。所得税については、確定申告の必要性を確認しましょう。
必要書類を準備し、確定申告の期限の確認や退職所得の源泉徴収票を保管してください。所得税の還付申告ができる可能性もあるため、確認しましょう。住所変更がある場合は、市区町村への届け出が必要です。
手続きを適切に行うと、退職後の税金関連の問題を防げます。わからないことがあれば、税務署や市区町村の窓口に相談してください。
退職手続きを進める際の注意点
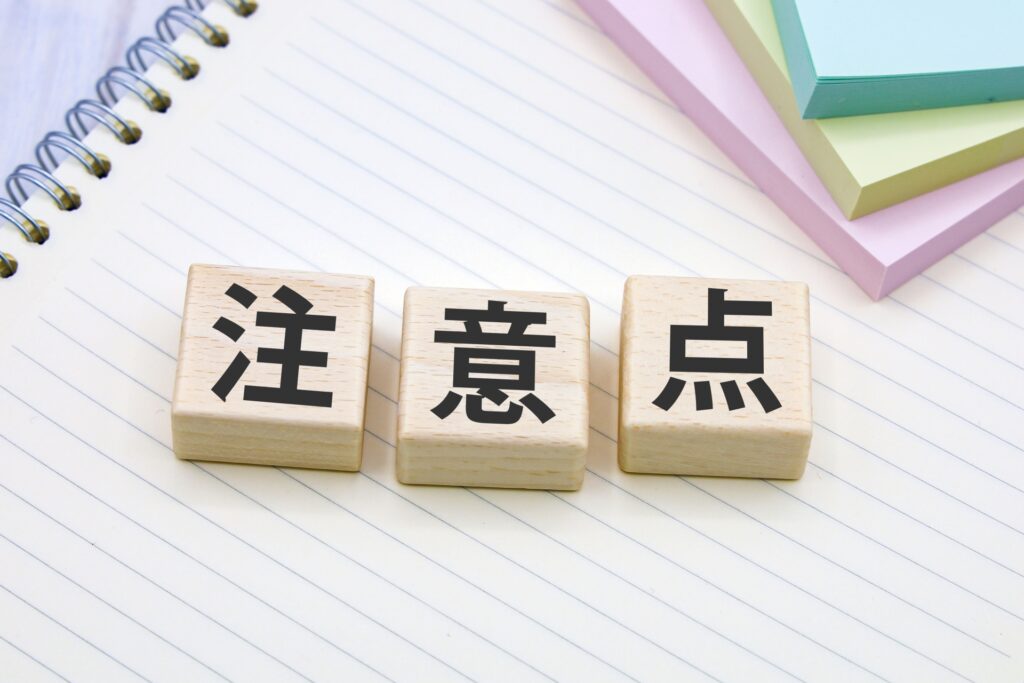
退職手続きを進める際の注意点を以下にまとめました。
- 会社の就業規則を確認する
- 退職までのスケジュールを立てる
- 必要書類と物品をリスト化する
会社の就業規則を確認する
会社の就業規則の確認は、退職手続きを円滑に進めるうえで重要です。具体的な確認項目は以下のとおりです。
- 退職の申し出期限
- 退職金の有無と条件
- 有給休暇の取り扱い
- 競業避止義務の有無
- 機密保持義務の範囲
- 退職後の連絡先提出
- 退職理由の記載
情報を事前に把握しておくと、トラブルを回避でき、スムーズに退職手続きを行えます。退職に関する規定を十分に理解すると、自分の権利や義務がわかり、適切な対応ができます。
退職までのスケジュールを立てる

退職までのスケジュールは、スムーズな退職手続きのために重要です。スケジュールを立てる際に意識すべきポイントは以下のとおりです。
- 退職日の設定
- 業務の引き継ぎ期間
- 有給休暇の消化予定
- 退職願・退職届の提出
- 健康保険や年金の切り替え
- 荷物の整理・撤去
- 取引先への挨拶回り
- 社内での退職挨拶
- 退職当日の流れ
- 退職後の手続き
スケジュールは想像以上に時間がかかる可能性があるため、余裕を持って立てましょう。
必要書類と物品をリスト化する
退職手続きを円滑に進めるためには、必要な書類や物品のリスト化が重要です。必要な書類や物品の一例は以下のとおりです。
- 退職願・退職届
- 健康保険証
- 会社から支給された物品
- 会社から貸与された資料
- 源泉徴収票(前年分)
- 年金手帳
- 雇用保険被保険者証
- 離職票
- 退職金の振込先口座情報
最終出勤日までの勤務時間記録や未精算の経費・交通費の請求書なども忘れずに準備しましょう。書類や物品を事前にリスト化し、チェックリストを作成しておくと、退職手続きの漏れを防げます。
まとめ

退職手続きは複雑で見落としがちな点が多いので、計画的に進めることが大切です。退職の意思表示から退職当日までの流れを把握し、必要な書類や手続きを確実に行うとスムーズに退職できます。就業規則の確認やスケジュール管理を徹底し、必要な書類や物品をリスト化すると効果的です。
退職後の健康保険や年金、税金の手続きも忘れずに行いましょう。事前に必要な情報を把握しておくと、無駄な手間やトラブルを回避できます。
ポイントを押さえて退職手続きを進めれば、新しい人生を円滑にスタートできます。