記事内に商品プロモーションを含む場合があります

高齢化に伴い、介護の需要は年々高まっています。自宅での介護を希望する人が増えており、訪問介護士の役割が注目されています。しかし、訪問介護士の仕事内容や必要な資格について詳しく知らない人がほとんどです。この記事では、訪問介護士の仕事内容や必要な資格、向いている人物像などを解説します。
記事を読めば、訪問介護士の仕事について理解を深め、自分に合っているかを判断できます。訪問介護士は、利用者の自宅を訪問し、身体介護や生活援助を行う専門職です。資格取得には、介護職員初任者研修の修了が最低条件です。利用者に寄り添い、臨機応変な対応ができる人に向いています。
» 介護の転職完全ガイド!
訪問介護とは自宅で行う介護サービスのこと

訪問介護について、以下の項目に分けて解説します。
- 訪問介護の対象者
- 訪問介護サービスの提供までの流れ
訪問介護の対象者
訪問介護は、自宅での生活に介護や支援を必要とする人を対象としたサービスです。要介護認定を受けた高齢者が対象となります。要介護認定を受ける状態の代表例は「認知症」や「寝たきり」です。生活環境として「独居」や「高齢者のみの世帯」の人も多く含まれます。
病気やけがなどで、一時的に介護が必要となる人も対象です。さまざまな状況や条件の人々が訪問介護の対象となるため、個々のニーズに合わせたサービスが提供されます。訪問介護は、自宅で生活を続けたい人々にとって大切な支援となります。
訪問介護サービスの提供までの流れ
訪問介護サービスの提供までの流れは以下のとおりです。
- 要介護認定の申請
- ケアマネージャーによるケアプランの作成
- 利用者や家族との面談
- サービス内容の決定
- 契約の締結
- 訪問介護計画書の作成
定期的なモニタリングと計画の見直しを行うことで、常に利用者のニーズに合ったサービスを提供し続けられます。訪問介護サービスの提供までには、綿密な準備と計画が必要です。一つひとつのプロセスを丁寧に行うことで、質の高い介護サービスを提供できます。
訪問介護士の主な仕事内容

訪問介護士の主な仕事は、利用者の自宅を訪問して介護サービスを提供することです。具体的な仕事内容は以下のとおりです。
- 身体介護
- 生活援助
- 外出介助
- 介護記録の記載
一人ひとりの状況に合わせた柔軟な対応が求められます。利用者の尊厳を守り、きめ細やかなケアを提供することが大切です。
» 介護職の仕事内容や必要なスキル、やりがいについて解説!
身体介護
身体介護では、利用者の日常生活をサポートし、生活の質の向上を図ります。食事介助や排泄介助、入浴介助、移動介助、体位変換などを行います。利用者の身体状況や生活習慣に合わせて行うことが大事です。食事介助では、利用者の嚥下機能に応じた食事形態を選び、ゆっくりと食べやすいペースで介助しましょう。
食事介助では食事の準備から後片付けまで、排泄介助ではトイレ誘導やおむつ交換、清拭を行います。入浴介助には、浴室への移動や洗身、着替えが含まれるのが特徴です。利用者の尊厳を守りながら行うことが大切です。移動介助ではベッドから車椅子への移乗や歩行介助を行い、床ずれ防止のために体位変換も定期的に行います。
身体介護には、以下の介助も含まれます。
- 服薬介助
- 口腔ケア
- 清拭・部分浴
- 整容介助
- 着替え
生活援助
生活援助では、主に家事全般の手伝いを行い、利用者が快適に暮らせるよう支援する仕事です。生活援助で支援する家事の内容は、以下のとおりです。
- 買い物の代行
- 衣類の整理・補修
- ゴミ出し・布団干し
- 食事準備と後片付け
- 洗濯物の収納
- 寝具の交換
- 室内の整理整頓
- 日用品の補充・管理
換気や室温調整といった細やかな配慮も、生活援助に含まれます。利用者の状況に応じて、薬の受け取りと管理のサポートも行う場合もあります。ただし、医療行為は行えないので注意が必要です。
外出介助

外出介助は、介護が必要な人の社会参加や生活の質の向上に大きく貢献します。具体的な支援の内容は以下のとおりです。
- 移動支援
- 車椅子操作・歩行介助
- 公共交通機関利用サポート
- 通院や買い物への付き添い
- 安全確保と見守り
外出前の計画立案や準備のサポートから、外出後の体調確認や休息の援助まで、一連の流れを支援するのが特徴です。利用者の体調や天候に配慮しながら、適切な介助を提供します。外出先での荷物の運搬や管理、必要に応じた排泄介助や食事介助も行います。
介護記録の記載
介護記録は、介護計画にもとづいて実施したサービス内容と状況を記載する仕事です。ケア中に起こった利用者の状態変化や気づいた点、特記事項、重要な出来事も、併せて記録します。客観的な事実と主観的な観察を区別し、時系列で簡潔かつ正確に記載することが大切です。
個人情報保護に配慮し、適切な表現を使用しましょう。介護記録は他のスタッフや医療関係者との情報共有にも活用されます。次回の訪問や介護計画の見直しに役立つ情報を含めると、より良いケアの提供につなげることが可能です。日時と記録者名も明記します。
定期的に上司や管理者の確認を受けることで、記録の質を保てます。
訪問介護士ができない仕事内容

訪問介護士ができない仕事内容は以下のとおりです。
- 医療行為
- 日常生活の範囲を超える家事代行
- 利用者以外へのサービス
医療行為
医療行為は医療従事者のみが行える仕事であり、訪問介護士には許可されていません。医療行為に該当するのは以下の行為です。
- 注射や点滴の実施
- 医薬品の使用や管理
- 医療機器の操作
- 床ずれの処置
- 痰の吸引(特定の研修を受けた場合を除く)
- 経管栄養の管理
- 人工呼吸器の操作
- 血糖値の測定とインスリン投与
- 導尿や浣腸
医療的判断を必要とする行為も同様です。医療行為が必要な場合は、訪問看護や訪問診療などの医療サービスを利用しましょう。訪問介護士は利用者の状態を観察し、異変があれば速やかに医療機関や家族に連絡を取ることが役割です。
日常生活の範囲を超える家事代行

訪問介護士は、日常生活の範囲を超える家事代行は行えません。訪問介護サービスの本来の目的から外れるためです。主に以下の家事が該当します。
- 大掃除
- 庭の手入れ
- 家族全員分の食事の準備や洗濯
- ペットの世話
家族の衣類の修繕や裁縫、家具の移動、大型家電の設置なども含まれます。安全面の理由から、窓ガラスの外側の清掃や高所作業を伴う掃除、電球交換、車の洗車、整備なども行えません。
利用者以外へのサービス
訪問介護は、介護が必要な利用者本人のためのサービスです。利用者以外の家族や同居人へのサービスは、訪問介護の対象外となります。家族や同居人への介護や家族のための買い物、料理、利用者不在時のサービスは行えません。親族や知人のための掃除や洗濯も同様です。
利用者以外の人へのサービスを求められた場合は、丁寧に説明し、理解を得る必要があります。利用者本人のケアに集中することで、より質の高い介護サービスを提供することが可能です。
訪問介護士の1日の仕事内容

訪問介護士の1日は、朝のミーティングから始まり、複数の利用者宅を訪問します。身体介護や生活援助、外出介助などを行い、各訪問後に介護記録を作成するのが特徴です。昼休憩を挟んで午後も同様の業務を行い、最後に事務所で報告書を提出し翌日の準備をします。
利用者の生活を支える重要な役割を担い、状況に応じて柔軟に対応する力が求められます。
訪問介護士に必要な資格
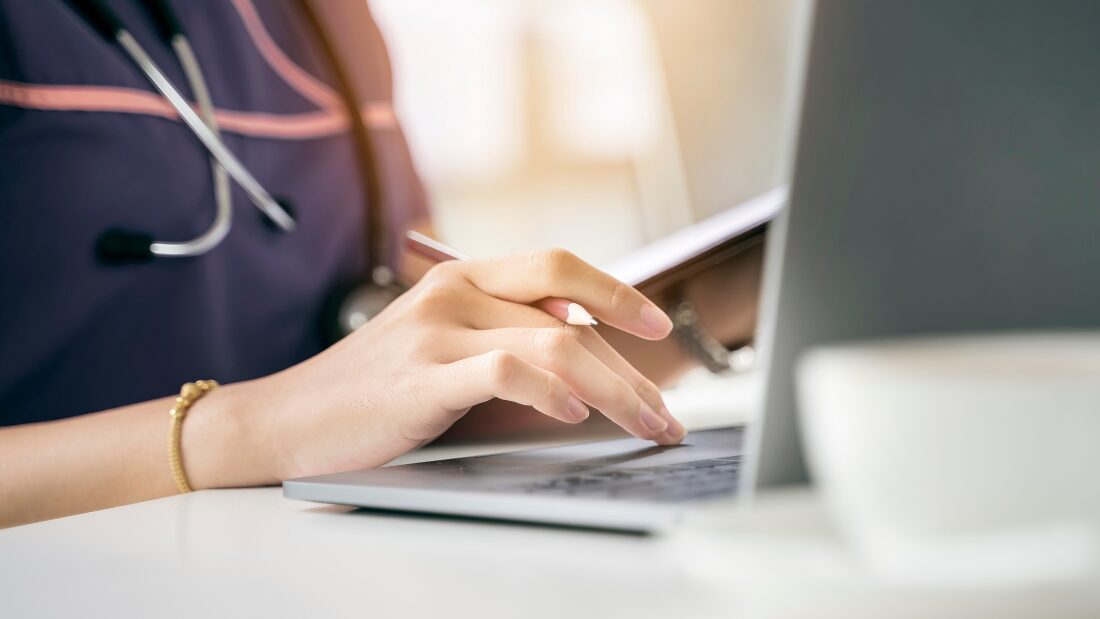
訪問介護士に必要な資格は以下のとおりです。
- 介護職員初任者研修
- 介護福祉士実務者研修
- 介護福祉士
介護職員初任者研修
介護職員初任者研修は、介護職員の入門的な資格です。旧ホームヘルパー2級に相当し、130時間の講習と試験を受けると取得できます。訪問介護や施設介護の基本的な知識と技術を学べるのが特徴です。カリキュラムには、介護の基本やコミュニケーション技術、生活支援技術などが含まれています。
実技演習も行われるので、実践的なスキルを身に付けることが可能です。研修を修了すると、訪問介護員として働けます。介護職への就職に有利になるだけでなく、将来的に介護福祉士を目指す人にとっても、重要な第一歩となる資格です。都道府県の指定を受けた民間の教育機関で受講可能で、一般的に10万円前後かかります。
通学制や通信制、eラーニングなど、さまざまな受講形態があるので、自分に合った方法を選べます。資格には有効期限がないため、一度取得すれば更新は不要です。
» 介護士とヘルパーの違い | 仕事内容や資格の違いを解説
介護福祉士実務者研修

介護福祉士実務者研修は、介護福祉士国家試験の受験資格を取得するための重要な研修です。450時間の講義と演習で構成されていますが、介護職員初任者研修修了者は320時間に短縮できます。研修内容は、以下の介護の専門知識や技術です。
- 人間の尊厳と自立
- 介護の基本
- コミュニケーション技術
医療的ケアの実技演習も含まれているので、より実践的なスキルを身に付けられます。一般的な受講期間は6か月~1年程度です。通信教育と通学を併用するコースが多く、休日開催のコースもあるため、仕事をしながらでも無理なく学習を進めることが可能です。
費用は15~30万円程度かかりますが、一部の自治体では受講費用の助成制度があります。
介護福祉士
介護福祉士は、介護職の中で最も上位に位置する国家資格です。資格を取得するには、介護福祉士試験に合格する必要があります。介護福祉士になるには、実務経験ルートや養成施設ルートなどがあります。
実務経験ルートは、介護の現場で3年以上働きながら介護福祉士実務者研修を受け、国家試験に合格して資格を取得する方法です。養成施設ルートは、高校卒業後などに、専門学校や大学といった介護福祉士養成施設で専門知識や技術を学ぶ必要があります。
卒業(または卒業見込み)と同時に(または卒業後に)国家試験に合格して資格を取得する方法もあります。資格を取得した後も、常に最新の介護知識や技術を身に付ける必要があります。
訪問介護士に向いている人

訪問介護士に向いている人は以下にまとめました。
- 利用者としっかり向き合える人
- 臨機応変に対応できる人
- 体力に自信がある人
介護や福祉に興味があり、学ぶ意欲がある人も向いています。
利用者としっかり向き合える人
利用者としっかり向き合える人は、訪問介護士に向いています。傾聴力と共感力が高く、利用者の話をよく聞き、気持ちを理解できることが大切です。利用者や家族、他の職種の人々と、円滑な意思疎通ができるコミュニケーション能力を持っている人が向いています。
利用者の心身の状態に根気強く向き合える忍耐強さや、日々の小さな変化やニーズに気づける観察力も、重要な資質です。思いやりの心を持ち、利用者に寄り添える人も、訪問介護士に適しています。信頼関係を築く能力があり、利用者の尊厳を大切にできることも重要な要素です。
プライバシーに配慮し、利用者の自立支援を心がけられる人も訪問介護士に向いています。利用者と良好な関係を築き、質の高い介護サービスを提供することが可能です。
臨機応変に対応できる人

訪問介護の現場では、利用者の状況は日々変化するため、柔軟な対応が求められます。利用者の体調や気分が急に変わったり、当初の予定にはなかった依頼やサービス内容の変更が生じたりする傾向です。体調の急変や転倒などの緊急時には、冷静な判断と迅速な行動が求められます。
多様な性格の利用者それぞれに合わせた関わり方も必要です。予期せぬ状況に冷静に対処し、創意工夫して問題解決ができる人も、訪問介護士に向いています。状況に合わせて、コミュニケーション方法を変えられる柔軟性も大切です。臨機応変に対応するには、幅広い知識と経験が必要になります。
日々の業務で多様な場面を経験し、対応力を磨くことが大事です。想定外の状況にも動じない精神力を養うことで、より質の高い介護サービスを提供できます。
体力に自信がある人
体力に自信がある人は、訪問介護士として活躍できる可能性が高くなります。訪問介護の仕事は、身体的な負担が大きいためです。体力が必要となる場面は以下のとおりです。
- 長時間の立ち仕事や訪問先への移動
- 移乗介助など、利用者の身体の支持
- 買い物袋など、重い荷物の運搬
- 家事援助などの身体活動
不規則な勤務時間や、緊急時の対応に耐えられる体力も求められます。季節や天候に関わらず外出するため、体調管理能力も重要になります。体力だけでなく、長時間の集中力と持久力も必要です。
まとめ

訪問介護士は、利用者の自宅で介護サービスを提供する専門職です。身体介護や生活援助、外出介助、介護記録の記載などが主な仕事内容となります。仕事に就くには、介護職員初任者研修や実務者研修、介護福祉士の資格が必要です。医療行為や過度な家事代行はできないといった制限もある点に注意しましょう。
訪問介護士に向いているのは、利用者としっかり向き合える人や臨機応変に対応できる人、体力に自信がある人です。訪問介護は、高齢者や障がい者が自宅で安心して生活するための大切なサービスです。専門的な知識と技術を持った訪問介護士の存在は、多くの人々の生活の質を向上させる助けとなります。